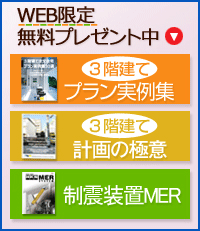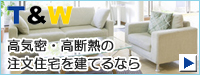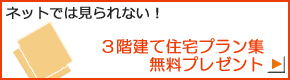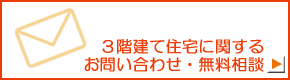コラム2
【木造3階建ての注文住宅を建てる際のポイントと注意点】
 限られた敷地を有効利用できる、建て込んだ敷地にも採光を取り入れることができる、眺望が臨める、と人気の木造3階建て住宅。
限られた敷地を有効利用できる、建て込んだ敷地にも採光を取り入れることができる、眺望が臨める、と人気の木造3階建て住宅。その一方、最近マスコミでたびたび報道されているのが、木造3階建ての欠陥住宅です。
「部屋の中を歩くと家がガタガタと揺れる」
「家にいると乗り物酔いをしたように気持ち悪くなる」
などなど深刻なケースが報告されています。
これらは単に施工業者の手抜きによって起きたものなのでしょうか?
そこで我社の建築構造の専門担当者から、3階建て木造住宅を建てる際のポイントと注意点について話してもらいました。
これから木造3階建て住宅を建てようと思っている方に、実際、木造3階建て住宅の構造設計に携わっている者として最近感じていることを述べたいと思います。
現在、木造3階建ては確認申請の際に構造計算書を添付して確認申請をしなければなりません。
平成12年6月より階数が2以上または、延べ面積が50m2を超える場合は、偏心率(バランスチェック)の検討が必要になりました。
【構造計算結果判定シートの例】 ※クリックすると拡大します







これは「バランスのよい建物を建てるように」という指導で、裏を返せば最近の木造3階建てはバランスの悪いものが多いということです。街を歩いてみても建物の間口に開口部を大きく設けてある(正面に玄関と車庫の出入り口があることが多い)建物をよく見かけます。この場合、バランスの悪い場合が多いようです。さらに、その玄関の庇を兼ねて2,3階が飛び出しているものもあり、こうなるとおせっかいにも「このような建物に住んでて平気なのかな」と思ってしまいます
どうしてそのように心配するのか、3階建て住宅を建てる際の下記3つのポイントを読めば、おわかりいただけると思います。
ポイント 地盤の事前調査と基礎はしっかりと
地盤の事前調査と基礎はしっかりと
地震、台風に対して抵抗し、建物を支えているのは「筋交い」「耐力壁」ですが、それが十分に力を発揮するためには、それを取り付ける金物、柱、梁そして基礎がしっかりしていないと、これらは働きません。特に基礎をしっかりと。ということは、地盤もしっかりとさせておくことが肝心ということです。
地盤については事前に調査をすることをお勧めします。以前、木造3階建ての構造設計の依頼があり、付近の地盤調査データに基づくと、ベタ基礎で大丈夫とふんでいたのですが、実際に敷地内地盤調査をした結果ベタ基礎では問題があるということが判りました。周辺のデータだけではその土地の地盤が同様とは判断しきれないということです。地盤というものはキチンと把握するのが難しいものなのです。
その地盤の調査方法ですが、「スウェーデン式サウンディング試験」というのがあります。敷地の状況によって異なりますが、費用は5万円位から10万円位です。住宅保証機構では地盤調査が義務付けられています。掛け捨て保険とでも思ってぜひとも地盤調査を行ってください。自分の土地の状態が判りますし、建ててしまった後では手の施しようがないという事態になることも考えられますので、地盤と建物の基礎に関しては手間と費用を惜しまないようにしてください。
ポイント 要所の部材にはこだわりを
要所の部材にはこだわりを
金物類はいろいろなものが出回っており、私自身、何を使おうか迷うことがあります。しかし、必ず大事なところには認定品または同等認定品を使用してください。
床下換気口を基礎の立ち上がり部分に設置している建物が多くみられますが、最近になって土台と基礎の間に取り付けるものとして、ゴム製で換気の役目を果たし、木材よりも耐熱性があり、防振効果も認められる木造建築用基礎部材があります。そのようなものを使用することからも建物の耐震性が上がると思います。
ポイント 確認申請と異なる施工をしない
確認申請と異なる施工をしない
それから確認申請と完成時の内容が変わっている建物が非常に多いというのも問題です。これはれっきとした違反建築なのです。
ところが、施主からの要望に対しプロとしてのアドバイスをしないまま施工会社が建築図面と異なる変更を加えることがあるようです。筋交い等の箇所が変わらなければ大丈夫と勝手に判断してしまい、確かに必要耐力壁は満足していますが、耐力壁の位置が変わると取り付ける金物が耐力不足になったり、柱梁等の部材を大きくする必要が生じる場合があり、バランスも当然変化するので悪化することもあります。
また、木造3階建ては風圧力で耐力壁の数が決まることが多いのです。周りに建物があるから少し位壁を減らしても大丈夫といって施主の了解をとり(施主からの部屋を広くとりたいという希望もあり)、壁をとって施工してしまう業者も中にはいるようです。
その点をよく考えて、安全確認を行う施工会社、設計者に任せることが大切になってきます。
家を建てる、もしくは買うということは精神的にも金銭的にも大変です。
とはいえ、基礎や地盤、構造といった建ててしまってからでは手の施しようがない大切な部分に関しては妥協しないでいただきたいと願います。
建物全体の強度や、部品同士の取り付け強度が重さや地震に対して安全であるかどうかを構造計算をもとに決定する作業のこと。
船舶や自動車でも行われます。
建物を建てる前に建設地の管轄の行政に提出する書類手続き。
建物が法律に基づいて計画されているかを確認する。
構造設計のときに検討した構造強度の計算書類のこと。
法律に基づいて計算式や強度の判定方法が決まっている。
建物の強度的な中心、重心から、建物をささえる柱や壁がどれくらい偏っているかまた、バランスが良いかの比率。
建物の階ごとの面積を足しあわせたもの。総面積。
建物の壁の中、もしくは柱と柱の間にはいっている斜め材。梁と柱、壁の変形を防ぐ役目がある。
建物をささえている構造的な壁のこと。
構造設計上、部屋と部屋を間仕切っている壁と区別している。
地盤の組成や、地盤の固さを調べた数値。いろいろな測り方がある。
建物の基礎のうち、建物の下前面をコンクリートで板状に基礎とするタイプのものを指す。
壁の下にだけ基礎があるものは布基礎と言います。
地盤の強さ(支持力度の強さ)を調べる簡易調査法の1つで、頭文字をとって「SS試験」ともいわれています。
敷地の四隅に先端がスクリュー状になった鉄の棒を差し、回転貫入させて地盤の強さを判定する地盤調査方法です。